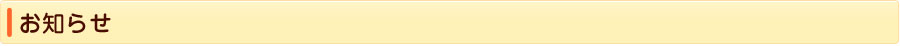
|
2013年12月18日 |
|---|
|
今年は例年以上に寒さの厳しい冬になるそうですね。 病院で働いていた頃は、寒くなってくると、入院される方が多くなるなという 印象をもっていました。 私の職種がリハビリ職ということで、どうしても脳梗塞や循環器疾患の患者さんを 中心に見ていたからかもしれません。
一方で、訪問看護、訪問リハビリにたずさわるようになって、病院から退院して、 自宅での生活を送る方々にサービスを提供するようになりました。 そして、気になるようになったのが、 「退院者数は、季節による変化があるのだろうか?」 ということです。
そこで非常に大まかな感じですが調べてみました。 厚生労働省では、全国の入院者数や退院者数の把握を行っており、 そのデータがしっかりとウェブサイト上に掲載されています。
これらをまとめて、大阪の一般病床(このデータでは、結核や精神病症も掲載されています)に限って 作ったのが次のデータです。
さらに、これをグラフ化してみると、
というような具合になります。
これを見てみると、1月、2月、5月、9月、11月が 退院者数が減っています(特に1月、5月、9月)。 そして、3月、7月、8月、10月、12月が退院者数が増加しています(特に3月、8月、12月)。 また、3月、8月、12月など大きく退院者数が増加した翌月(9月、1月)は大きく減少しています。 こうしてみると、寒い、暑い、暖かいなどの気候的なものはあまり関係ないようです。
ここで、3月、12月の翌月となる4月、1月は、1年の内でもひとつの区切りとなる月ですね。 8月はお盆?で、これもひとつの区切りと言えば、言えなくもなく・・・。 (「お盆までには、家に帰りたいな―」という台詞も時々耳にしていたような) もしかすると、退院に際しては、こうした一つの期間的な区切りが関係しているのかもしれません。 そして、そういった区切りを超えても退院できない方々というのは、病状などからなかなか退院が難しく、 なかなか退院者数の増加へとつながっていかないのでしょうか。
在宅サービスに関わる者としては、1月や9月というのは利用者数が大きく減り、 3月や8月そして12月は利用者数が大きく増える可能性があるというような流れを 予想しながら準備をしておく必要があるのかもしれません。
|